バーバリアンファームを訪ねて
4年前の2019年6月、わたしたちPUMPQUAKESは、東京のインフォショップIRREGULAR RHYTHM ASYLUMの紹介で、当時、福島県西会津にあったバーバリアンブックスにふたりを訪ねたことがあった。それ以来の再会となるが、そのあいだの彼らの活動はSNSなどで見ていたし、Zineを通して広島県北東部の庄原市に移住し本格的に農業をはじめたことや、家族が増えたことは知っていた。しかし、実際に彼らがどのような風景のなかで暮らし、どのようなことを考えながら農業を営むようになったのか、それは同じ場所に身をおいて、主体的に考えてみないと知り得ないことのように思えた。それは、オアハカでの経験で学んだことでもある。そこで、実際に、彼らを訪ねてみて、その後もやりとりを重ねるなかで見えてきたいくつかの事柄をここに記したい。

2022年11月、広島県北東に位置する庄原市にあるバーバリアンファームへむかった。そこここに紅葉する山々の稜線に添うように、空には雲が横たえている。稲刈りを待つ田んぼのあいだを縫いながら、細くつづく道をのぼっていくと、民家が見えてきてバーバリアンファームのふたりが笑顔で迎えてくれた。

▲我が娘が飛びついていった、モモエさん(左)とウィルさん(右)
グラフィックデザインのはたらき_ITWST(I Think We’re Still Thinking)
楢崎萌々恵(以下、モモエさん)とウィリアム・シャム(以下、ウィルさん)は、グラフィックデザインユニットとしてニューヨークの美大を卒業後した2014年にその活動をスタートさせた。ユニット名である、「ITWST」は「I Think We’re Still Thinking(まだ考え中)」に象徴されるように、彼らのデザインワークは、早急に答えを求めずじっくり思考し、世に問いかけてゆくような批評性と、独自のユーモアを兼ね備えている。また、自分たちのメディアとしてZine*1の制作を多数手がけてきた。

▲筆者の所有するバーバリアンブックスのZine。これでもほんの一部で、彼らは2023年3月時点で、Zineを#37まで出版している(https://www.barbarianstore.net/product-category/zine/)
モモエさん
「さまざまな仕事を経験しながらも、二人でzineをつくることはずっと続けてきました。それは、私たちのおおもとに、クリティカルデザインへの関心があるからです。Zineというメディアも、もともとパンクの人たちが刷って、自分たちの思いを発信するという流れがあるわけですけど、グラフィックデザインも昔は、政治や社会と密接にリンクしたものでした。いまは、アドバタイジング(広告)としてのグラフィックデザインが世の中で主流になってしまっています。でも、政治や社会と深く結びつき批評性をもつグラフィックデザインが、ウィルはもともと好きだし、わたしもそのデザインのはたらきが大切だと思っています。農園をやっていても、自分でメディアを持つことや、出版などはずっと続けていて、いまもこれからも、変わらずやっていくだろうなと思います」
個々に制作するものもあるけれど、二人でつくる場合は、とにかくたくさん話し合うという二人。日常生活での違和感からはじまり、社会や政治、環境問題のことなど、Zineの共同制作の作業を通じて、互いの考えを深く知るきっかけにもなっていると話す。
モモエさん
「大学でウィルと出会って、ウィルがいろんな本とか紹介してくれたけど、最初は、ちょっと警戒していました。でも、だんだん社会や政治の問題を、紹介してもらった本なども参考にしながら勉強していくうちに、無知ってこわいなと思うようになったし、ショックを受けました。それで、自分でも学ぶようになったら、当初、ウィルとのあいだに感じていたギャップもこの6、7年で埋まってきました。ウィルはウィルで、最初はもっと過激だったけど、丸くなったというか……笑。表現方法やアプローチの仕方が変わったように思います。そのきっかけになったのは、やはり西会津でバーバリアンブックスというコミュニティスペースをやっていた時の経験です。それまで転々と拠点を移していた私たちが初めて地域の一員となって、さまざまな背景・世代の人々と暮らす日々のなかで、私たちの視界は大きく広がっていきました。ウィルの文章の内容も、以前はもっとラディカル(過激で急進的)だったし、わたしがその翻訳をやったりもしていたのですが、それじゃあ伝わらないよねっていうことを、肌で感じられたのはほんとうに良い経験でした。ウィルが伝えたいことをまずは英語で書いて、私がいろんな人に伝えていくために翻訳し、イラストやデザインで中和する役割というか。そういうバランスでやるようになっていきました。ウィルが書いたものを読んでみて、『へえ、そうなんだ』と学ぶことはいまだによくあります」
西会津での経験/生活者として、労働者として
二人にとって、大きな分岐点となった福島県西会津での日々。ニューヨークから西会津に拠点を移すきっかけとなったのは、「地域おこし協力隊」で、グラフィックデザインの職能を地域のなかで活かせる場があるかもしれないと思い応募した。結果としては、「地域おこし協力隊」としでではなく、西会津国際芸術村のレジデンスアーティストとして迎え入れられることになり、2016年に西会津に移り住んだ。一年間の滞在期間のなかで地域の人々との関係性が築かれていき、もっと地域の人たちに学びたいという思いが大きく膨らんだ。そしてなにより自然に囲まれた西会津での生活は、都市生活が長かったふたりにとっては新鮮で驚きの連続だったけれど、味わったことのない心地よさも感じたそうだ。そこで、翌年からは、レジデンスアーティストとしてではなく、西会津で一生活者として暮らすなかで、「バーバリアンブックス」をやってみたいと考えるようになった。

◀2019年にPUMPQUAKESのメンバーや友人たちとバーバリアンブックス(福島県西会津)を訪ねたときの様子
私たちが2019年に訪ねたバーバリアンブックスは、「五十嵐呉服店」という看板の残る元呉服店を「バーバリアンブックス」の拠点とし、通りに面した土間に印刷機などを並べ、上がり口のスペースにこれまで制作してきたZineなども配架しつつ、
「勉強、仕事、読書、休憩やお茶飲みなどいろいろな形で利用してみてください」
と呼びかけ、コミュニティ&プリントスペースとして地域の人たちにこの場を開放していた。
また、西会津で暮らすうちに、ウィルさんは農家の方の手伝いを、モモエさんは保育園でも働くようになった。
モモエさん
「最初は、西会津に“アーティスト”や“デザイナー”という肩書をもって、入ってきたわけですが、一度それを捨てて、一生活者として暮らすようになってコミュニティスペースを開いたら、知り合う方たちも、子どもや、農家の方や保育士さん、おかあさんたちというふうに今まであまり縁がなかった方たちと出会うようになりました。あと、保育士の仕事もしてみると、さまざまな問題や課題も見えるようになってきました。ウィルはウィルで、農協でアルバイトを始めたり農家の方たちの仕事を手伝うようになって、今まで私たちにはコレしかないんだと思っていた肩書きがどんどんとれていった。そしたら、なんか二人とも精神的に楽になって。もちろん自分たちは表現者としていたい気持ちもずっとあるんですけど、でも、今まで以上に生活者の声、労働者の声が染みわたるように聞こえてくるようになったんです。そして私たちとしても、自分たちが一生活者として、一労働者として持ち得る視点が大事に思えるようになってきました」
ウィルさん
「大学生のときに、ボランティアでデンマークなどに無農薬の農業をやっている農園に働きにいったりもして、そのあたりから農業に関心がありました。でも、本格的に農業に向き合い始めたのは、西会津から。西会津の人を通じて、農家になることを具体的に考えるようになりました。というのも、西会津に暮らすうちに、地域社会と自分たちの暮らしがどのように相互作用し、自分たちの心と体がどのようにつながっているのかを理解するうえで、“食べ物を育てること”は自分たちにとって必要不可欠な要素になっていったし、一日の大半を外で過ごし、爪の間に土を溜めながら植物の世話をする時間が、このうえなく幸せで平和なようにも感じられました。あと、スケートボードも農業もたくさん練習しないと上手にならないけど、それが面白いと思ったし、大変だけど、自分で時間を自由に決められることと、ボスがいないという自由さがあります」
「バーバリアン(Barbarian)」が問いかけるもの
そんなふたりが福島・西会津での「バーバリアンブックス」を経て、広島移住後に「バーバリアンファーム」を始めた。そこでも引き継がれたのは「バーバリアン(Barbarian)」という言葉だ。訳語としては「野蛮人、文明化されていない、未知の、危険な部外者」というネガティブな意味合いで表現されることが多い。しかし、そこでふたりは問いを投げかける。「そもそも誰が誰を野蛮人と呼ぶのか?」「なぜ自分たちがよく知らない考えや思想を無視し、否定するのか?」と。

◀バーバリアンファームのポスター
「等身大の家族農園。学ぶこと、育てること、食べるもの、楽しむもの。広島県庄原市で野菜など作っています」
そのような視点に立つと、「バーバリアン」という言葉は、現代のわたしたちに必要な疑問を投げかけるキーワードになり得るのではないかとふたりは考えた。そして、その「文明化されていない新しいアイデア」をこの農園で実践していこうと、「バーバリアンファーム」という新たなプロジェクトがたちあがっていったのだ。
2021年にバーバリアンファームから発行されたZine『GROWING FROM ZERO(ゼロから育てる)』では、「なぜ食料を生産するのか?」「生活としての農業」「支払える額を支払う(?)」等を章立てとし、農業を本格的に始めた頃の試行錯誤やバーバリアンファームの背景にある思想が綴られている。
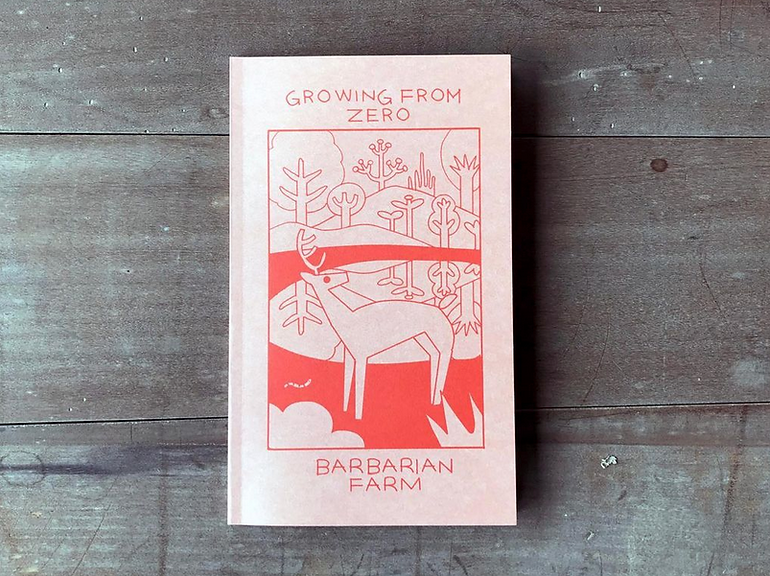
◀Zine『GROWING FROM ZERO(ゼロから育てる)』
なかでも興味深いのが、小規模農業=ヒューマンスケールでの農業の実践(手作業といくつのかの道具で管理可能)を選択するに至った経緯や、Pay What You Can(支払える額を支払う)を設定し、消費者に食糧生産に関する真の労働力について考えてもらおうというアイデアを実際に試していることだ。
それらは、食物でさえも大量生産・大量消費を促す資本主義社会とそれゆえに大規模化する農業システムに抗うものであり、さらには、どのようなライフスタイルを自分たちが望んでいるのか、あらためてじっくり考えてみるきっかけにもなる。そして、私たちが消費者として土地と切り離された安価なものをやみくもに消費し続けることではなく、消費という行動自体が、地域や生産者を支える側面もあることを、野菜を通じて直に問いかけている。その意味では、彼らの生産する野菜もまた、Zineのようなメディアとしても機能しているとも言えるのではないかと感じた。
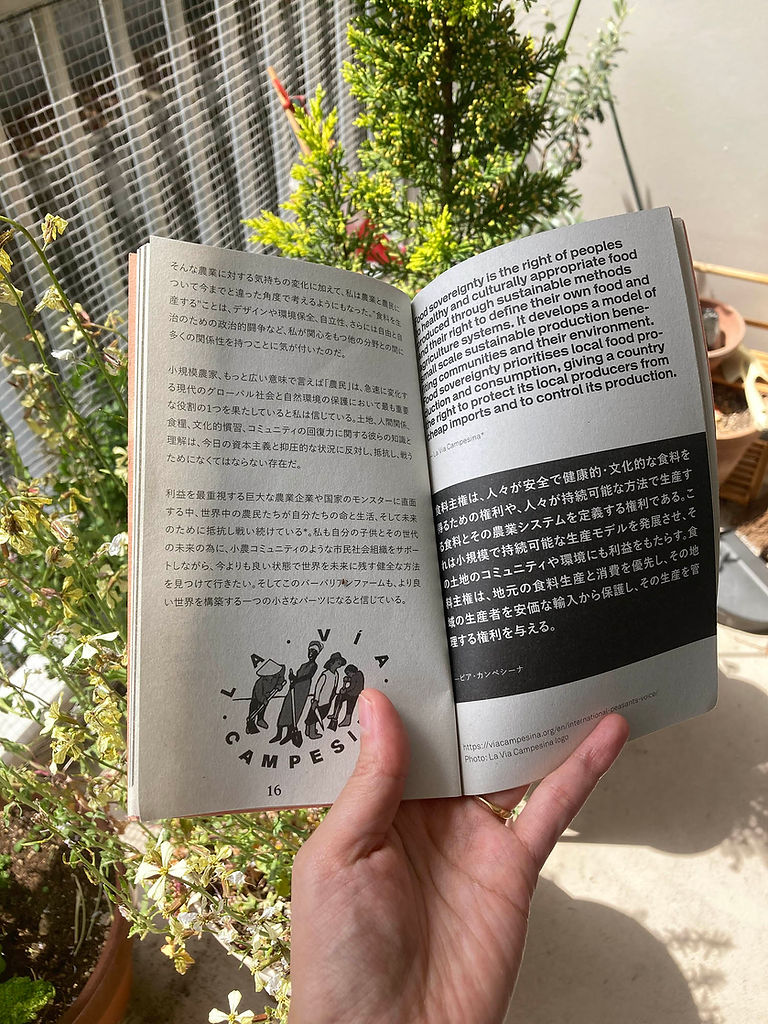
彼らはまた、Zineのなかで、メキシコのサパティスタ(Zapatista)*2の言葉や、ヴィア・カンペシーナ(La via Campesina)*3による食料主権の考えも紹介している。
そのうえで「土地、人間関係、食糧、文化的慣習、コミュニティの回復力に関する彼ら(農民)の知識と理解は、今日の資本主義と抑圧的な状況に反対し、抵抗し、戦うためになくてはならない」とウィルさんは語る。バーバリアンファームもより良い世界を構築するひとつのパーツになることを目指していて、さらには若い世代にも、農家を職業のひとつとして選択肢にいれるイメージができるよう、もともと都市生活者で、農地や農機具も持っていないところからどのように農家になっていったのかを、つまびらかにZineのなかで語ってくれている。私たちを巣食う「資本主義」が、自分にどこまで影響を及ぼしているのか、私たちは洗いざらい確認してみる必要があるし、自分たちが望むべき暮らしのかたちを、同時代の別地域での実践に学ぼうとPUMPQUAKESでも、ラテンアメリカの「Buen Vivir(よき暮らし)」という考え方を援用し、アイデアをシェアしてきた。そうして、あらためてバーバリアンファームのふたりの話を聞いていると、さらに踏み込んだ実践がなされていて、とても励まされたし、今後もお互いアイデアや近況報告をしていこうと、約束した。
畑にかさなるいくつもの風景
滞在中、家からすこし離れた畑に繰り返し足を運んで、作業を手伝わせてもらったりもした。バーバリアンファームはヒューマンスケールでの農業にとりくんでいるが、大型の機械を使わず最小限の道具だけでおこなう農業は、からだを最大限に使うことなんだと思い知った。まだ仄暗い早朝から日が暮れるまで、自然のなかで身体を最大限に使いながらの仕事。
「ウィルは、バーバリアンファームを始めてから、ほとんど休みはなくて、土地からも離れられなくなった」とモモエさんがその背中を見つめながら教えてくれた。めぐる季節のなかで、身体を通して自然との交渉を重ねていることが、その仕事の手つきから感じられたし、農業とは風景そのものをつくる営みなのだということが、山を背景にしてひろがるバーバリアンファームを見ているとダイレクトに感じられた。そして、農という仕事を含めた衣食住すべてで、彼らの生を表現しているように思えた。
もとは耕作放棄された土地に、種を蒔き、手をかけて、食物をつくる。いろんな野菜が肩を並べながら光を受け、風に揺れている様子は、土の持っているポテンシャルを目に見える形で見せてもらった気がしたし、なによりバーバリアンファームの野菜はエネルギーに満ち満ちていておいしかった。そのおいしさが、どこからくるのかというと、やはり関係性だと思う。どのような場所で、どんなふうに手をかけられ、ここにあるのか。彼らが日々どんなことを考え、なにを選択し、私たちがそれをどう支持したのか。そのなかだちに、野菜がある。それは食の自治についての話でもあると思う。







バーバリアンファームを始める前、さまざまな土地を訪れたウィルさんは、パレスチナのオム・スレイマン農園や香港のマポポ・コミュニティ・ファームなど、「農業による抵抗」をおこなってきた人々のもとを実際に訪ねていた。
「デモの最前線でバリケードをつくる代わりに、向けられた銃に石を投げる代わりに、争われる土地の土を耕し、植物や命を育て、人びと健康なコミュニティを共有することで、創造することの大切さを伝えていた」
と、ウィルさんはそのふたつの農園についてZineでも紹介しているけれど、ウィルさん自身が耕す畑には、パレスチナや香港で実際に訪ねた農園の風景も、きっとかさなって見えているだろう。どこにも行けなくても、自分たちの足元を具体的に耕すことで連帯したり協働したりする方法があることを、その姿で示してくれた。野菜の梱包作業をする納屋には、世界中の自律的なコミュニティのポスターやバナー、ステッカーなどが貼られていて、ラジオからは世界中のニュースが聞こえてきた。

おわりをつぎのはじまりに
納屋の一部をDIYでコツコツ改修していて、ゆくゆくここを、コミュニティ・ストアとしてひらきたいとふたりは話す。「道の駅みたいに、自分たちで育てた野菜やその加工品、それからZineも直接販売できたらいいな。あとはスケートボードができる場所もつくりたい。みんなが気軽に寄り集まって、支え会える場所をつくっていけたら」と話は尽きない。

最後にもう一度バーバリアンファームに立ち寄った。畑の入口には、花が植えられていて、そこに「誰をも歓待する心」をあらためて見た気がしたし、その風景を心底美しいと思った。

▲モモエさん(左)、息子さん(中)、ウィルさん(右)バーバリアンファームにて
仙台に戻ってからも、バーバリアンファームで見た風景を何度も反芻しながら、私たちが次にやるべきことを考えていた。宮城に住みながら、これまではあまり接点のなかった農家の方たちを訪ねたり、農や食にまつわる本を読んだり……と、しばらく慌ただしく過ごした。
久々にモモエさんに連絡してみると、2022年末、ウィルさんは新型コロナウィルスに感染し、特にひどい症状に見舞われたのだという。体調不良が約一ヶ月ほども続き、農作業も出来ず、そんななかベッドで考えていたのは、次の農業にまつわるZineで「燃え尽きる」をテーマにすること。こんなに症状がひどかったのは、「身体がこれ以上働けない、働きたくない、休まなければならない」という状態になっていたからだと感じたそうだ。だから、そのときの心境を反映して、暗い内容のZineになるだろうけど、春になって、体調も精神も回復したら、もっとポジティブなものも作るかもしれない」と教えてくれた。こんなふうに、良いときばかりではなく、うまくいかないときのことも吐露してくれることが、ときに励ましになる。
実は、かくいう私たちも、年明けに家族全員で新型コロナウイルスに感染し、私とまだ0歳の娘の症状は重く、回復までひと月ちかくを要した。なにごとも一足飛びにはいかないし、こんな状況にいるときこそ、身近で支えてくれたコミュニティのありがたさを実感した。そして、それをなんとか乗り越えたいま、あらためて、互いの大変な時期をねぎらい合える相手がいることはなによりも心に効いた。バーバリアンファームから「みんなのエネルギーになりますように」と野菜が送られてきたときは泣きそうになった。病み上がりで感傷的になっているだけと言われるかもしれないが、それだけではないという感覚がある。
この感覚がどこから来ているのか考えていたとき、朝日新聞に寄稿された宮城在住の漫画家いがらしみきおさんの「『神様のない宗教』から12年」の記事をみつけた。いがらしさんはこの記事のなかで、震災後、私たちが失い続けているのは「人を信じること」ではないか?と問いかけていた。
…その時の被災地に満ちていた『人を信じる』という空気感は、文化としての宗教しかないように見えた日本の中で、まるで『神様のない宗教』のようだと思った。
それから12年を経て、今私が感じているのは「我々はなにかを失い続けているのではないか」という漠然とした不安だ。(中略)
不確かな人生を生きていくには、どうしてもなにかを信じたくなる。(中略)自分の意思でもなく、なにも知らずにこの世に生まれてきたものが、世界に満ちている暴力と貧困と差別に気付かされる瞬間はとても痛ましい。我々の誰にもその瞬間はあったはずだが、そのあと我々はなにを信じて生きてきたのだろう。
それは人ではなかったか。その「人」がただの隣人であったり、街で見かけた「いい人」だったり、まだ一度も会ったことのない誰かだったとしても。(中略)
信じるということは、人生という自分の持つ限られた時間を、信じるものへと差し出す覚悟のことだろう。ワンタッチや、ワンクリックではなく、その信じるもののところまで、歩いて行かなければならない。 (朝日新聞2023.3.29 いがらしみき寄稿「『神様のない宗教』から12年」より抜粋)
コレクティブリサーチと称して、これまでメキシコ・オアハカのコレクティブのリサーチや、今回、バーバリアンファームを訪ねたりと各地へ出向いてきたが、この根底にはやはり震災の経験がある。当時の被災地で見られたいわゆる災害ユートピア的状況に励まされ、その意味を確認し合いながら活動してきたが、復興の大きなうねり(政治的な意味も含む)のなかで、市民の自律的で細やかな活動は下火になり、立ち止まって考えることは許されず、うやむやな行き場のない感覚だけがあとに残された。だからこそ、私たちはもう一度、「信じたい」のだと思う。それは、パンデミックで疲弊し分断され、ロシアの戦争で何万もの死者がいまだ出続けている絶望的な事実、その先には暗澹たる未来しか見えてこないからこそ、「人に会い、話し、同じ風景をみる」という具体的なことを通して、自分たちの望む未来のために、どのように生きていくか、覚悟を決めたいのだとも思う。そして日々、剥奪され続ける人間性を回復し、人間のちからをもう一度信じたい。
私の目に「覚悟を決めた」ように映るバーアリアンファームのふたりは、どこか清々しく、それでいて優しい。それは、きっとこの場では語られなかったことも含め、清濁あわせ呑んだうえで、それでもこうやって生きていくと覚悟し、受け入れた人に宿るなにかだとも思う。それは、モモエさんのアートワークやウィルさんの言葉にも現れていると思う。最後にそれらをここにシェアしたい。
モモエさんのアートワーク

s o c i e t y
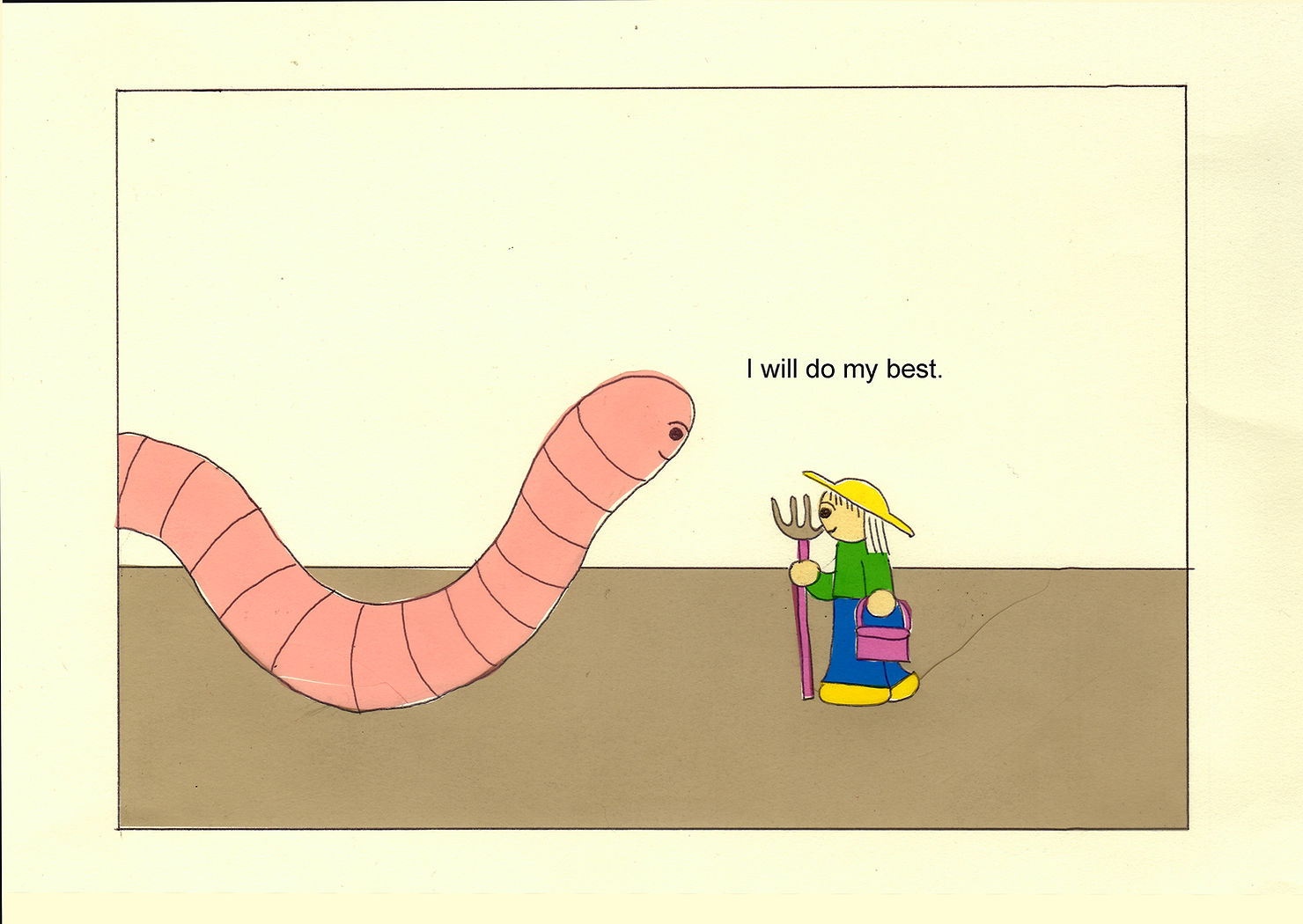
earthworm sensei

耕して育てて分け合おう、春だ

April showers bring May flowers 4月の雨が5月の花をつれてくる
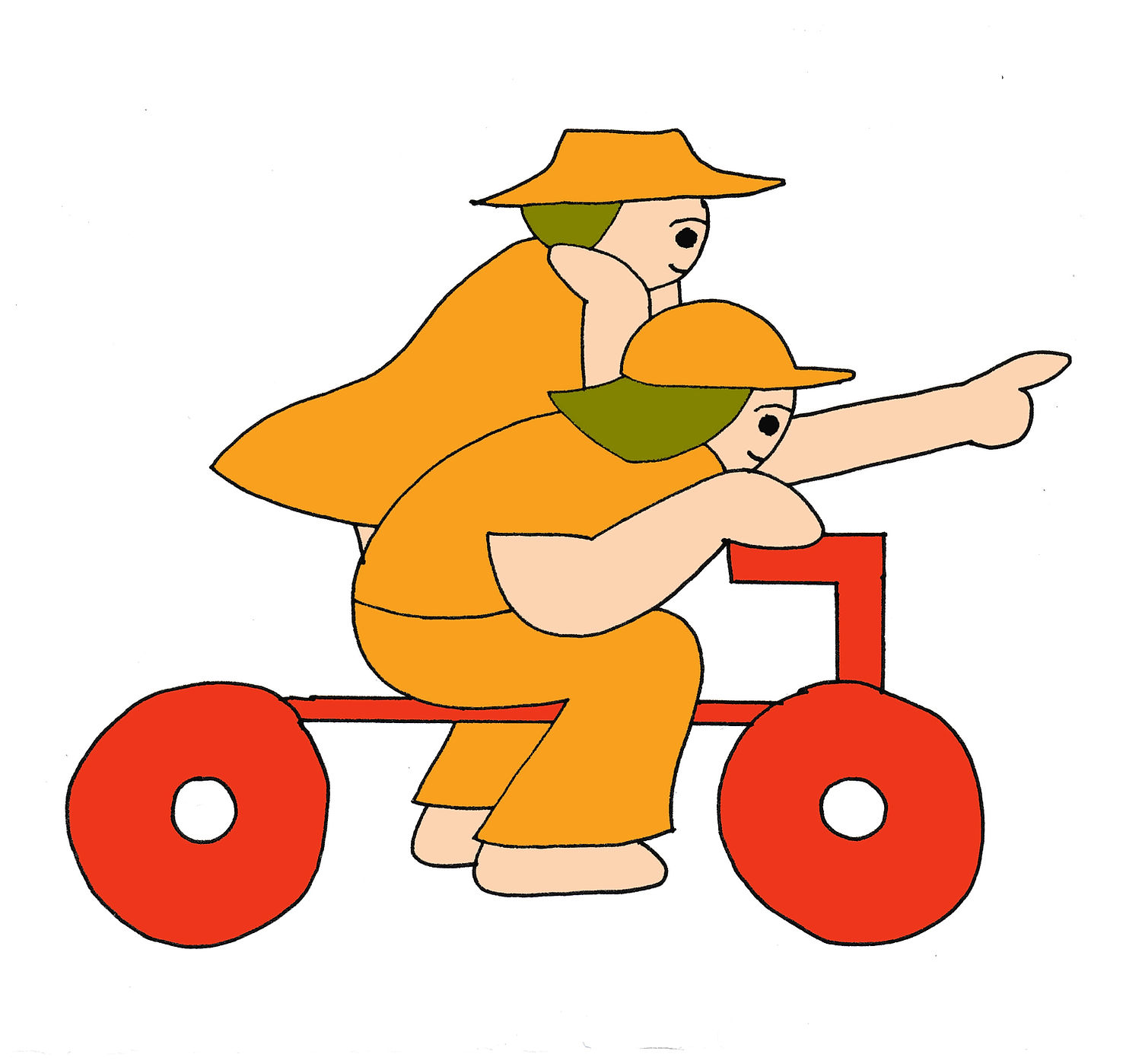
I love you Autumn, please slow down

Power to all the people holding the seeds of the future
ウィルさんからのメール
I don’t think it’s possible to separate one’s political ideas from everyday life. Whether we’re conscious about the meaning of our actions or not, I think we’re always shaping the world we’re inhabiting. Personally I want to change the diseased society we’re all unfortunately stuck in, while also doing my best to make a healthier planet. Becoming a parent, farming, making art: these are the small ways I choose to spend my time doing that I believe are meaningful and inseparable from my own beliefs about society.
政治的な思想と日常生活を切り離すことはできないと思っています。自分の行動の意味を意識する/しないにかかわらず、私たちは常に自分の住む世界を形づくっているのだと思うのです。個人的には、私たちが不幸にも陥ってしまった病的な社会を変えたいし、地球をより健康的な状態にするために最善を尽くしたいと思っています。親になること、農業をすること、アートをつくること、これらは私が選んだ小さな時間の過ごし方であり、社会に対する自分の信念と切り離せない意味のあることだと信じています。
執筆後記
記事でも触れたメキシコのサパティスタの自治学校を、私と長崎はメキシコ滞在中に訪問したことがあるが彼らの運動を知るきっかけになったのは、サパティスタが、メキシコからの独立や政権転覆などを目的とした反政府運動ではなく、世界的な新自由主義グローバリゼーションがもたらす構造的な搾取と差別に対して戦うことを目的とした運動をインターネットを通じて広く世界中に呼びかけていたからだ。もちろん個別の社会的背景や政治状況は異なるけれど、その差異に目を凝らすばかりで分断を生んできた現在、むしろ、「より良い世界」が意味するものをそれぞれ地場で検討しながら、ともに動ける部分をみつけて実践していくことのほうがさらに重要に思える。そのために共感覚をどのように持っていけるか、東北のなかでの南型知を形成するための試行錯誤を今後も、実際に足を運び人や場に出会いながら続けていきたい。
テキスト:清水チナツ
写真:長崎由幹
———————-
Zine*1:zineとは「magazine」または「fanzine」の略で、個人または少人数のグループなどで自主的に出版される出版物。作者個人の考えや主張を反映し編まれた冊子で、コピー機やリソグラフ、インクジェットプリンターなどで印刷し、ホチキスなどで簡易製本される。分業化された商業出版に対し、ZINEは印刷・製本・流通など、制作物が読者に届きまでのあらゆる作業に作者自身が関与する。歴史を遡ると、19世紀後半から20世紀初頭のアメリカにおけるアマチュアプレス運動や、1920年代から1930年代にかけて続いた黒人によるハーレム・ルネサンスの文学雑誌など経済的・政治的に阻害された人々が自らの主張を発信するためのメディアとして自主的に刊行した出版物が最も初期のZINEのルーツとされる。(参照:https://ja.wikipedia.org/wiki/ZINE)
サパティスタ*2:サパティスタ民族解放軍。メキシコで経済的に最も貧しいとされるチアパスを中心として活動するマヤ系先住民主体の農民組織。1994年1月1日に武装蜂起し、ラカンドンの密林を拠点に闘争を続け、貧困のままに放置された先住民の人権が守られるよう政治の体制変革を主張した。また、インターネットを介して自らの主張を大々的に展開し、世界中からの支援を獲得したため、武力などを行使せずとも隠然たる影響力をメキシコ政府に持つようになった。(参照:http://www.ezln.org.mx/)
ヴィア・カンペシーナ(La via Campesina)*3:1992年に設立された、中小農業者・農業従事者組織の国際組織。世界69カ国、148の農業組織により構成されている。自らの土地で食糧を生産する権利を指す「食料主権」という概念を用い、1999年以来、市場原理主義に基づく「農業改革」に抗すべく世界的なキャンペーンを展開している。(参照:https://viacampesina.org/en/)
———————-
助成:公益財団法人 仙台市市民文化事業団「2022年度 持続可能な未来へ向けた文化芸術の環境形成助成」
